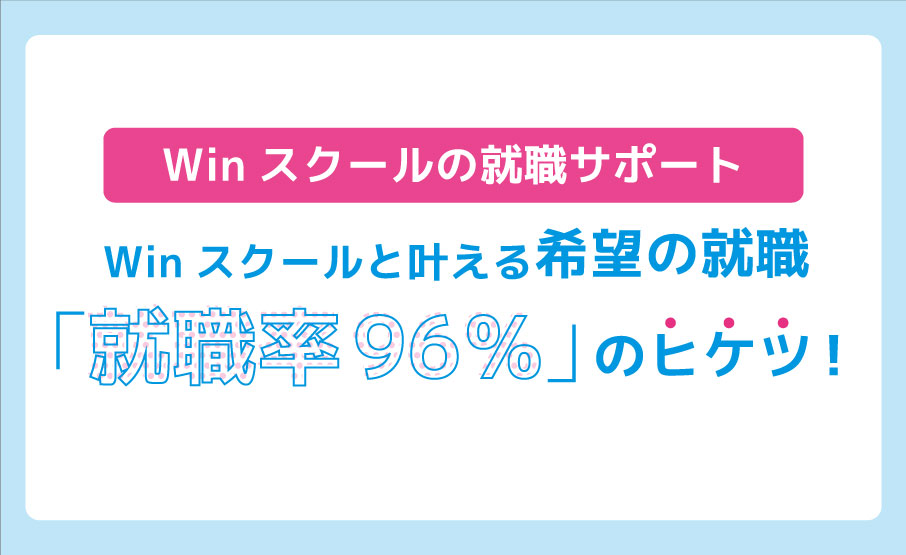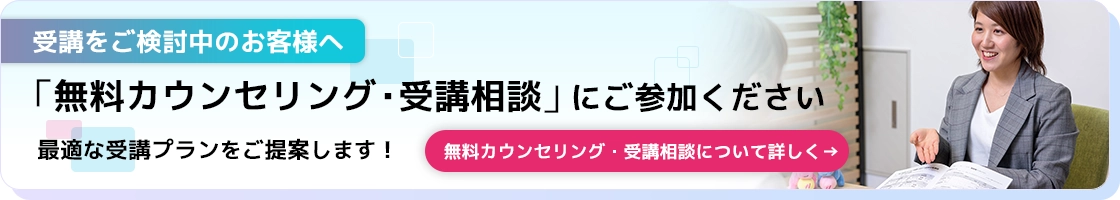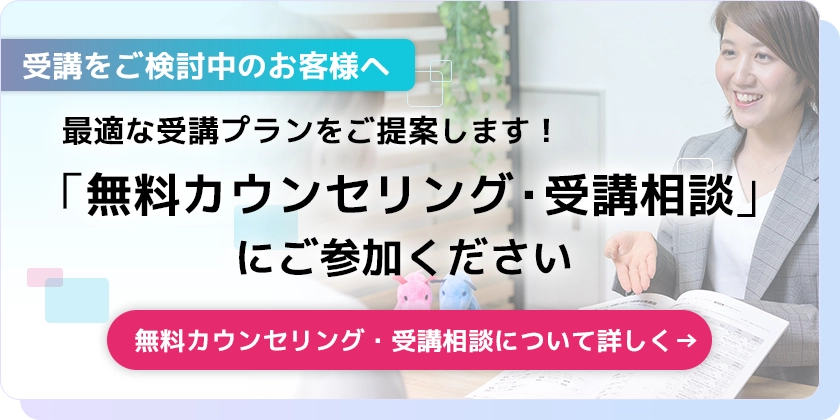Winスクールの法人研修サービス
事業を進めていく上では、業務効率化やDXを常に検討していかなければなりません。しかし、具体的な方法についてあまり知識がない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、人事部や部下の教育を検討する方に向け、業務効率化に必須の「5S」について解説します。
5Sとは

5Sとは、職場の環境改善を目的とした活動のことで、各フェーズである「整理」「整頓」「清潔」「清掃」「しつけ」の5つのローマ字表記の頭文字をとったものです。
これらのプロセスを通じて、日々の業務を効率化したり、生産性を向上させることが期待できます。
整理:不要なものを選別して処分する
5Sの最初は「整理」、すなわち「不要なものを処分する」ことからはじめます。
オフィスを長く使っていると、不要な道具や資料を放置したまま仕事をしていることがあります。不要なもの、処分したいものにシールを貼るなどし、計画的に処分することを心がけると良いでしょう。
整頓:必要なものだけを使える場所に
整頓とは、必要な道具やツールなどをあらかじめ所定の位置に置いておくことです。整頓は、利用頻度と業務フローの観点から整理されるべきです。
例えば、カメラや録音機器など、よく使うガジェットはまとめて所定の位置に、持ち出すものはリストに「使用中」と記載するなど、備品の管理を徹底すると良いでしょう。
清潔:常に清潔にしておく
清潔は、「整理」「整頓」「清掃」を徹底し、汚れがない状態を保ち続けることを指します。
清潔な環境のためには整理、整頓、掃除を属人化させずに、チーム内でルール化しておくことが必要不可欠です。
オフィスを常に清潔にしておくことで、取引先など社外からの印象も良くなります。
清掃:掃除とチェックを怠らない
掃除は、職場内のゴミや汚れを掃除し、常に綺麗な状態に保つことを指します。掃除が行き届いていないと、職場の印象が悪くなったり、そこで働く人のモチベーションを下げるなど、さまざまな観点でデメリットが生じます。
清掃を行うことで、普段あまり気にしない場所の不具合や散らかりが目に付くようになり、オフィスの問題を早期発見することができます。
しつけ:4つの「S」を習慣づける
しつけは、上記の4つのSを習慣づけるための教育、指導、ルールづくりのことを指します。ルールを明確化すれば、各人の責任の所在も明らかになり、一人ひとりが自分事として職場の環境改善に働きかけることができます。
5Sの目的

企業が5Sを実行する目的は、生産性の向上、働きやすい環境づくり、離職率の低下の主に3つです。
生産性の向上
生産性の向上は、あらゆる企業が追求するべき目標です。5Sを実行することで、これまで無駄に費やしていた時間を削減することができるでしょう。
例えば、デスク周りや共有スペースを整理整頓しておくことで、必要な資料を探す時間が省け、生産性を向上させることが期待できます。
働きやすい環境づくり
資料や什器などが散らかった職場では、情報漏えいや資料の紛失、重要な機材やツールのメンテナンス不足などが発生することがあります。
このように、整理整頓や掃除が行われていない環境は、企業活動のあらゆる面においてリスクが生じることになります。
デスクや共有スペースに5Sが徹底されていれば、資料の紛失などのミスを防げるとともに、従業員が日々感じるストレスを最小限に抑えることができるでしょう。
離職率の低下
散らかった環境は精神衛生にも良くありません。デスクや共有スペースにものが溢れている状態では、タスクを整理することが難しく、従業員のオフィスへの満足度が低下してしまいます。
従業員のオフィスへの満足度の低下はそのまま従業員の離職にもつながります。企業にとって必要な人材の維持は最優先事項です。5Sを徹底し、人材の流出を避けましょう。
5SがDXにつながる理由

5Sを進めることで、自動化できるタスクと必要なPCスキルが明確になり、DXの足掛かりになります。
まず、5Sによる現場の業務を改善する意識は、タスク管理に役立ちます。5Sはオフィス内にいるメンバーのタスクの明確化・見える化にもつながるため、明確になったタスクをツールなどで自動化・共有することで、DXの足掛かりになるでしょう。
また、5Sにより社内の課題が明確になれば、それぞれに必要なPCスキルも明確になります。例えば、5Sを徹底することで無駄な業務が明らかになった場合、エクセルのマクロやバックオフィスツールの操作などのスキルが求められるようになるでしょう。
5SはDXの環境を整える最も基礎的な業務改善です。急激なDXばかりにとらわれず、まずは足元の環境を見直すことからはじめてみてはいかがでしょうか?