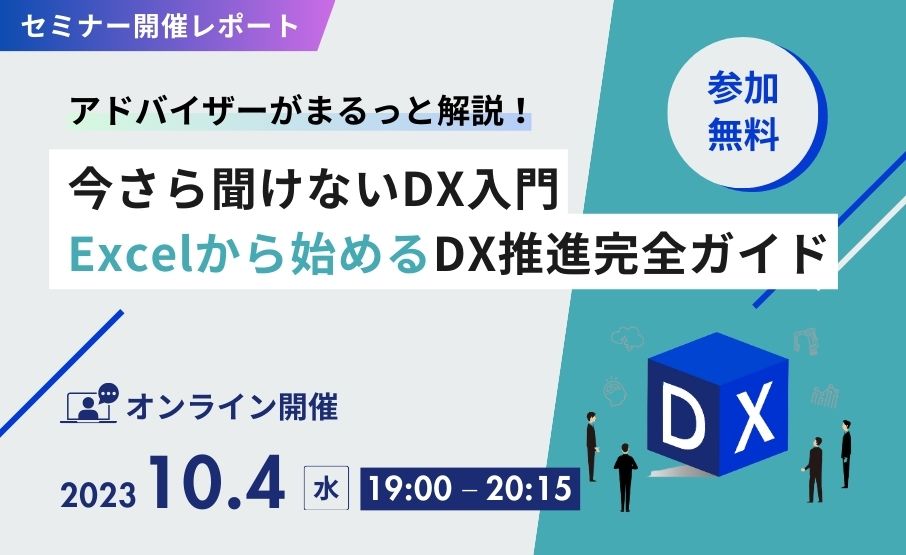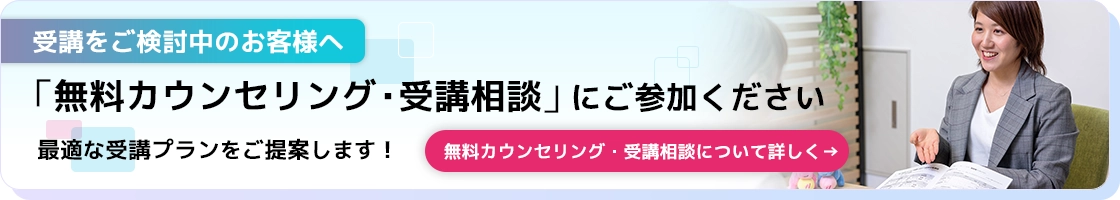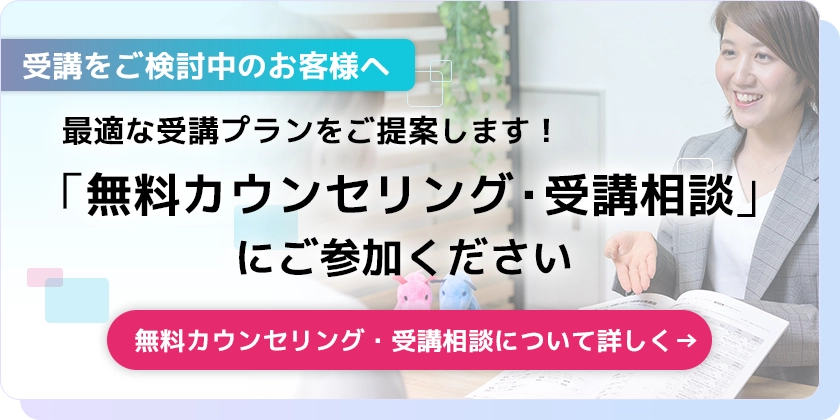今、産業界のさまざまな場面で語られているDXですが、もしかしたらDXをデラックスと読んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、「最近やたらDXという言葉を聞くけれど、DXってそもそも何?」というビジネスパーソンのために、DXのいろはについてわかりやすく解説します。
DXは企業の将来性に関わる重要なものなので、ぜひこの機会に知識を身につけましょう。
目次
DXとは
DXの定義
DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略ですが、頭文字を取るなら「DT」になるはずですよね。しかし、Transformationの「Trans」が英語圏で「X」と略されることから、DXという表記になっています。
ただそう聞くと、「言葉ってむずかしい」や「何だか面倒くさい」というのが、皆さんの本音かもしれません。
では実際に、DXはどのようなことを指すのでしょうか。国は以下のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、 プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
※経済産業省「DX推進指標」より引用
先ほどの頭文字に続いて、何だかわからりづらいですよね。
なので、簡単にいうと、
企業がデジタル技術を使って、仕事のやり方やビジネスのしくみ、社内の文化を大きく変えること
という認識で良いかと思います。
なぜ、DXが必要なのか?
DXが必要な理由を一言で語れば、それはテクノロジーの急速な進化です。昨今、IoTやChatGPTをはじめとする生成AIなど、デジタル技術がどんどん進化しています。
そのため、従来のシステムや方法に頼っていると既存の製品・サービスは世の中の変化に追いつけなくなり、結果として企業は市場競争に勝てなくなってしまうのです。
実際に、顧客のニーズも変化が激しくなっています。
たとえば、
- 商品を買うのは通販サイトだけど、店舗で実物を見てみたい
- レジに並ばずキャッシュレスでスムーズに決済したい
- オンラインで気軽に推し活を楽しみたい
のように、昭和から平成の時代には少なかった需要が顕在化しているのです。
また、労働環境も人口減少やライフスタイルの変化、残業規制に伴う物流の2024年問題などにより人材不足が深刻な課題となっています。
その他、システムの老朽化や熟練の技術者の引退により従来のシステムの修繕が困難など、企業の課題は山積しています。
こうした背景から、DXを推進しないことは「2025年の崖」と呼ばれる経済損失の危機であり、各企業は迅速な対応を迫られているのです。
DXとIT化は何が違う?
DX=IT化じゃない!
DXの意味や定義を知ると、「それってIT化のことでしょ!」と思った方は多いのではないでしょうか。しかし、DX=IT化ではありません。
IT化とは、主に既存のアナログ的な業務をデジタルツールに置き換え、効率化することを指します。たとえば、紙で行っていた文書管理をパソコンのファイルに変えることや、手作業の計算をソフトウェアで行うようにすることです。
つまり、IT化は現行の業務フローは基本的に変えずに、デジタル技術で単純な効率化を図るプロセスと言えます。
DXの実現に必要な3つのフェーズ
国の定義では、DXは3つのフェーズを経てその実現を目指します。それは、1.デジタイゼーション→2.デジタライゼーション→3.デジタルトランスフォーメーションです。

※経産省DX支援ガイダンスP4より引用
- デジタイゼーションとは、IT化の一部でアナログな情報をデジタル化するプロセスです。これは、手書きの記録をExcelやデータベースなどに変換し、データの保存や検索を簡素化します。そういう意味では、IT化の範囲に含まれますが、単に情報のデジタル化にフォーカスしているのがデジタイゼーションの特徴です。
- デジタライゼーションとは、デジタイゼーションから一歩進んだ状態で、デジタル化したデータを活用して業務プロセスの見直しや最適化をすることです。たとえば、顧客データをCRM(顧客管理システム)に統合し、営業担当がリアルタイムで顧客情報を共有するなど、効率的な営業活動を行います。つまり、デジタル技術を使って、業務の進め方そのものを変えることを意味します。
- デジタルトランスフォーメーションとは、DXの最終段階で、デジタル技術を活用してビジネスモデル全体を変革することを指します。単に業務を効率化するのではなく、新たな製品やサービスを生み出し、顧客に提供する価値を高めるために組織文化の改革も行います。
DXとIT化の違い
DXとIT化の違いは、デジタル技術の活用範囲や目的が異なることです。IT化は主に効率化を目的としている一方、企業が掲げるビジネスのあり方や顧客との関係性を再構築することがDXの本質です。
多くの企業が人手不足の中、IT化は大前提ですが、それ以上に各企業はDXを推進してこそ持続的な成長やイノベーションにつながります。
DXの具体的事例
DXの内容は何となく理解したけれど、具体的に何がどう変わるのでしょうか。実際の業務からイメージできるDXの段階別に具体的事例をお伝えします。

デジタイゼーションの事例
医療機関のカルテのデジタル化
病院では、患者の診療記録を紙のカルテで管理していましたが、それをデジタル化したことにより、迅速かつ効率的な情報の検索・共有ができるようになりました。医師や看護師は、患者の治療履歴や検査結果を即座に参照できるため、診療の質が向上したと言えます。
製造業の設計図のデジタル化
製造業では、紙ベースで管理されていた設計図をCAD(コンピューター支援設計)ソフトでデジタル化する例が増えています。紙の図面をデジタルデータにすることで、設計変更が容易になり、他部署や工場間での共有もスムーズになります。こうしたデジタル化は、製造プロセスの改善や製品のクオリティ向上にもつながります。
デジタライゼーションの事例
人事労務管理のクラウドシステム導入
従来、従業員の勤務状況や給与計算は紙やExcelで管理していましたが、それらをクラウドベースの人事労務管理システムに移行することで、データの共有と処理が大幅に効率化されました。社員自身で勤務状況をオンラインで入力したり、システムが自動的に給与計算を行ったりすることで、労働時間や給与に関する処理が迅速かつ正確になります。
物流のトラッキングシステムの活用
物流業界では、トラッキングシステムを導入することで、配送中の商品やトラックの位置情報をリアルタイムで追跡できるようになりました。これにより、配送スケジュールの管理が正確になり、遅延が発生した場合でもスムーズな対応が可能です。また、顧客に対しても正確な到着予定を提供できるため、顧客満足度は向上していると言えます。
デジタルトランスフォーメーションの事例
Amazonによる消費行動の変化
Amazonは、買い物の形を根本から変えたデジタルトランスフォーメーションの典型例と言えます。従来、私たちは店頭でモノを買うのが当たり前でした。
しかし、Amazonはオンラインショッピングのプラットフォームを確立し、どこにいてもスマホで簡単に商品を購入できるようにしました。さらに、Amazonは物販だけでなく、Kindleでの電子書籍やPrime Videoでの映画・ドラマのストリーミング配信などデジタルコンテンの提供も拡大し、顧客満足度を大幅に向上させています。
こうしたビジネスモデルの変革により、買い物やエンターテインメントの消費行動が大きく変わり、Amazonは単なるオンラインショップから広範囲なサービスを提供する企業へと進化しました。
Uberによる市場の拡大
Uberは、スマホアプリを使って移動手段である車を簡単に呼べるしくみを作り、従来のタクシーよりも便利で透明な料金システムを確立しました。ライドシェアは、日本ではまだ普及しておりませんが、Uberがタクシー業界のビジネスモデルを大きく変えたことは間違いないでしょう。
またUberは、Uber Eatsというデリバリーサービスを始め、飲食業界にもデジタル革命を起こしました。これは、レストランや小売店が新たな顧客にアプローチできるようになっただけでなく、配達員の人手不足の解消や副業の促進にもつながっています。
このように、デジタル技術の活用は、市場のさまざまな場面で新しい収益源を生み出していると言えます。
まとめ〜DXって結局どうすればいい?
DXの導入は段階的に
DXに取り組んでいない企業がいきなりAIを活用するといったことはハードルが高いですよね。そのため、DXで最初にやるべきことは、まず自社の状況をしっかりと分析して何が必要なのかを把握することです。
その上で、改めてDXについて整理してみましょう。
- デジタイゼーションは、アナログをデジタルに変えること
- デジタライゼーションは、デジタル化されたデータを活用して業務を効率化すること
- デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術を使ってビジネスのやり方や組織の文化を根本から変えて、イノベーションや持続的な成長につなげること
もし、デジタル化がまだ進んでいないなら、デジタイゼーションから始めて業務の効率化を目指します。次に、デジタライゼーションで業務プロセスを最適化し、その後でデジタルトランスフォーメーションを進めることが大切です。
DXは企業にとって避けられない未来ですが、段階を踏んで着実に進めることで競争力を強化し、持続的な成長を実現できると言えます。