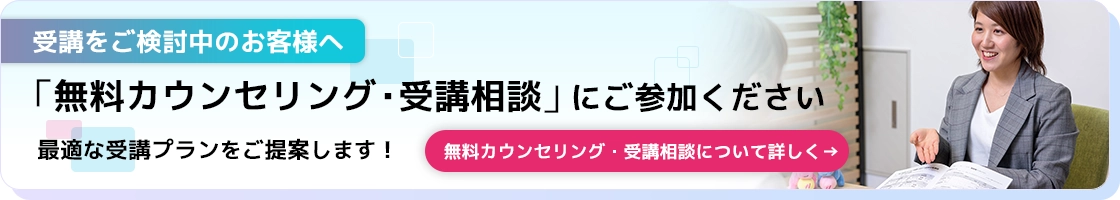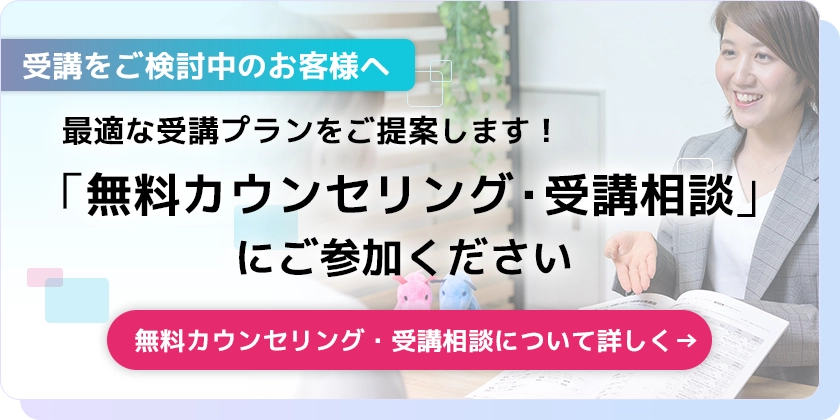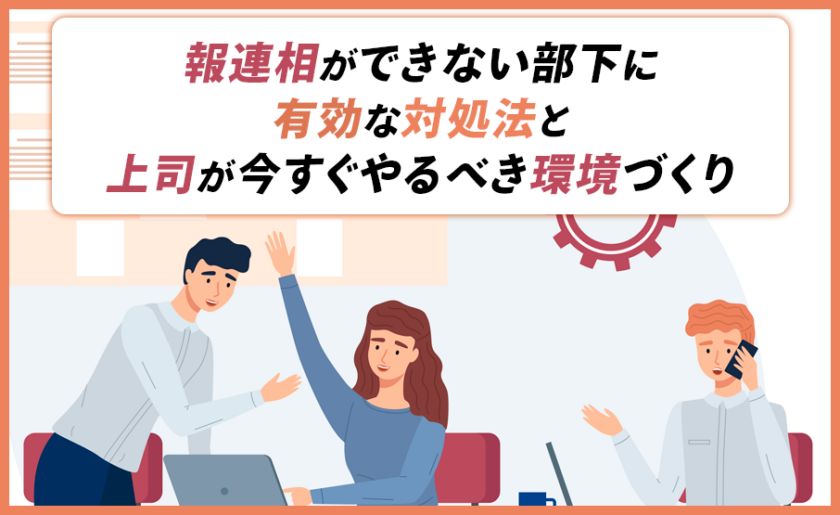
ビジネスの現場で重視される報連相ですが、新入社員や未経験者の中には報連相をしない・できないという人が少なくありません。ただ仕事を進める上で、顧客とはもちろんのこと、上司や先輩社員とのコミュニケーションがスムーズにとれないと生産性の低下を招く恐れがあります。
この記事では、報連相のできる従業員を育てるコツや環境づくりにより、企業の生産性を高める方法をお伝えします。
報連相ができない部下の心理とは?
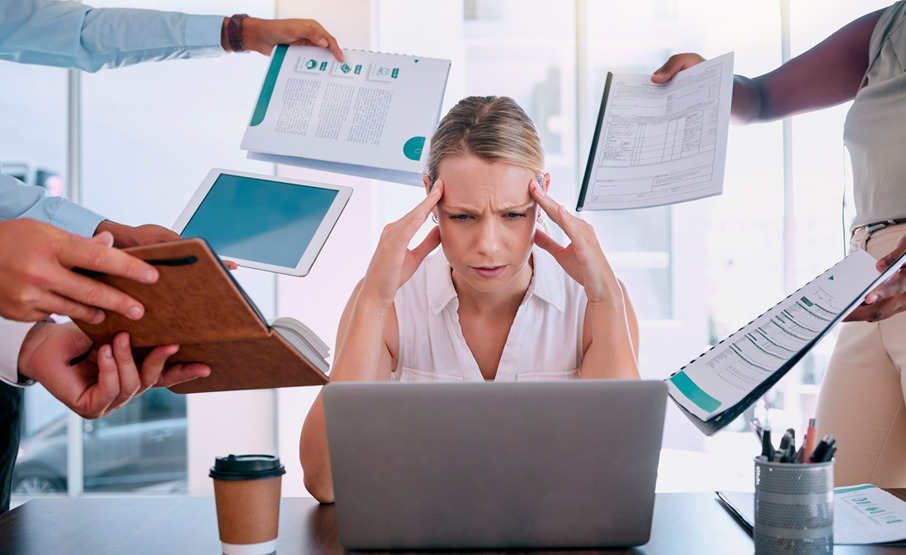
報連相ができない部下をやみくもに叱りつけたり、注意したりしても恐らく状況は変わらないでしょう。むしろ、部下との人間関係は悪化してしまいます。そのため、まずは報連相ができない部下の心理を知ることが必要です。
報連相の必要性を知らない
報連相ができない部下の中には、報連相の必要性を感じていない人が一定数います。彼(彼女)らはきっと報連相の目的や大切さを知らないもしくは理解していないため、必要ないと判断するのでしょう。
しかし、企業に属して働く場合、多くの仕事は指揮命令系統があります。また業務の進捗状況を顧客と共有することが一般的です。
そのため、すべてを個人で完結する仕事でない限り、作業プロセスにおける担当業務の前後やトラブル発生時は必ず自分以外の人も対応します。だからこそ、報連相の必要性をきちんと説明することが大切です。
慣れない作業で余裕がない
新入社員や未経験者は与えられた作業をこなすのに精一杯という人が少なくありません。そのため、上司の求める報連相ができないことはよくあります。
このとき、報連相=社会人の常識みたく注意するのはNGです。なぜなら、注意された側は一生懸命やっているのに自分を否定された気持ちになるかもしれないからです。
部下がまだ仕事に慣れていない場合は、上司から積極的に声をかけ、様子を伺うようにしましょう。
タイミングがわからない
報連相の必要性は理解しているけれど、タイミングがわからないという人もいます。また「相談する=自分で解決できない」という後ろめたさからタイミングを逃してしまい、結果的に仕事が遅れたり、トラブルが広がったりすることもあるでしょう。
他にも「上司も仕事をしているのだから時間を使わせるのは申し訳ない」と変に気を遣って、報連相をしないケースがあります。ただこれらは、コミュニケーション不足の可能性があるので、上司は部下にプレッシャーとならない程度に声がけすることが必要です。
上司がやるべき部下への声がけ

仕事をスムーズに進めるには、部下とのコミュニケーションを積極的に図り、報連相の重要性を理解してもらうことが必要不可欠です。そこで、上司に必要な声がけ事例を3つご紹介します。
1.必要な報連相と不要な報連相
報連相の必要性を説明することは非常に重要ですが、部下が担当する業務の1から10まで報連相を求めていたら、返って生産性は下がります。そのため、必要な報連相と不要な報連相の違いを説明することが大切です。
必要な報連相とは、進捗状況や課題の共有・チームで連携しないと進まない作業・ミスやトラブルが発生したときに行うものです。一方、不要な報連相とは、情報を求めていない場合や既知情報、意思決定に影響がないものを指します。
2.不安感に寄り添う
部下の中には、慣れない作業のせいか「失敗したらどうしよう」とか「ミスを責められたくない」といった不安を抱える人がいます。こうした不安を払拭するためには、日頃から対話を重ね、何かあったら部下が積極的に相談してくる環境づくりを心がけることが必要です。
たとえば、「何かお手伝いできることはありますか?」「ここまでの作業で問題はありますか?」「わからないことがあれば、遠慮なく相談してくださいね」などの声がけが有効と言えます。
3.自己評価を高める
部下の生産性を向上させるには、部下自身の自己評価を高めることも大切です。そのため、「この作業はとてもよく進んでいますね」と仕事の早さを褒めたり、「あなたの成長を見守っています」と安心感を与えたりすることで、部下にとって報連相をしやすい環境となります。
これらの声がけは、部下が業務に取り組む上での不安やストレスを解消し、自信をつけることができる効果があります。ただし、過剰な声がけは部下の自主性を奪う可能性があるため、相手の状況や個性に応じて適切なバランスをとることが重要です。
部下との共有が必要な報連相のルール

部下とのコミュニケーションが上手くとれるようになったら、より円滑な業務を進めるために、報連相のルールを共有しましょう。
不測の事態が発生したら…
不測の事態が発生した場合は迅速な対応が求められます。そのため、事前にフローを決めておくことで、部下は混乱を避けて効率的な行動ができるようになります。
たとえば、速やかな報告→担当者の決定→上司の判断→顧客への報告・説明→復旧・改善のように、対応フローが決まっていれば、部下が報連相のタイミングを逃すことはないでしょう。
ミスや失敗したときの対処法
部下がミスや失敗をしたとき、最も大切なことは、部下にきちんと報連相をさせる体制を整えることです。
たとえば、認識・把握→確認・原因分析→説明・指導→対応策の決定・実行→確認・フィードバックのようなフローを予め部下と共有しておきます。そうすることで、部下は上司を信頼して適切な報連相を行うようになります。
ちなみに、部下のミスや失敗を責め立てたり、自己否定したりすることはNGです。そういう体質は報連相どころか隠蔽につながりますので注意しましょう。
生産性を高める報告の仕方
報連相の中でも報告は、口頭でも書類でも簡潔でわかりやすい内容が好ましいと言えます。たとえば、結論を先に伝えて、その理由や背景を時系列で説明する方法です。
部下に報告を求めるときは、こうした効率の良い報告の仕方を予め説明しておくことで、お互いに時間の浪費となる報告を避けることができます。
従業員の生産性を高める環境づくりとは?

上司は部下が報連相をしやすい環境を心がけることが大切ですが、企業全体の生産性を高めるためにはさらに一歩進んだ従業員のための環境づくりが求められます。
明確な目標設定
企業全体の生産性を高めるにはまず、従業員一人ひとりが何をすべきなのかを明確にすることが重要です。そのため、従業員毎の目標を設定し、それが達成されたときにどのような成果が得られるかを共有します。
効果的なフィードバック
次に、従業員の報連相に対して適宜フィードバックを行います。フィードバックは、成果が得られたときは賞賛し、問題が発生したときは共同で解決策を見つけるための指導に必要なものです。
従業員はフィードバックによって自ら学習し、自己評価を行うようになるので、課題解決能力を身につけてもらうためにも有効な手段と言えます。
モチベーションの維持・向上
仕事に対するモチベーションが低いと業績に影響を及ぼします。そのため、従業員のモチベーションを維持・向上させる方法として、やりがいや目的の共有が必要不可欠です。
とりわけ仕事に慣れない段階においては、相手を勇気づける声がけによりエネルギーを与えることがモチベーションの維持・向上につながります。
このように、従業員の自己肯定感を高めたり、計画的に行動を支援したりする環境づくりが企業全体の生産性を高めると言えます。
まとめ〜即戦力を求める企業、教育の機会を求める従業員
企業として「従業員には即戦力となる人材になってほしい」という本音がある一方、従業員側は教育やコミュニケーションの充実を求めています。報連相にはこのバランスを調整する潤滑油のような役割があるので、企業は従業員が報連相をしやすい環境づくりを心がけることが大切です。
ただそうはいっても、教科書通りに進まないのがビジネスの現場でもあります。Winスクールでは実際の業務を想定した研修により、質の高い報連相と課題解決能力を養うことが可能です。
自社での人材育成に課題を抱えている企業様は導入を検討してみてください。