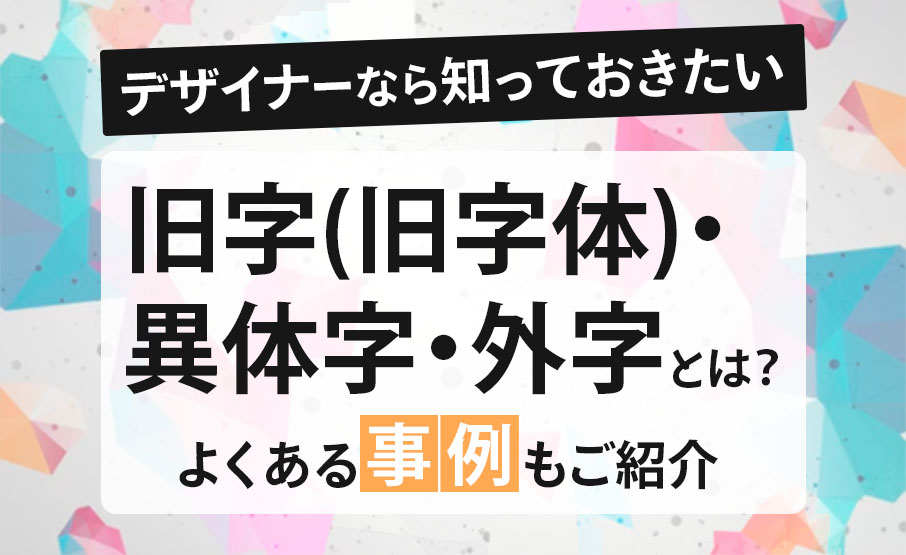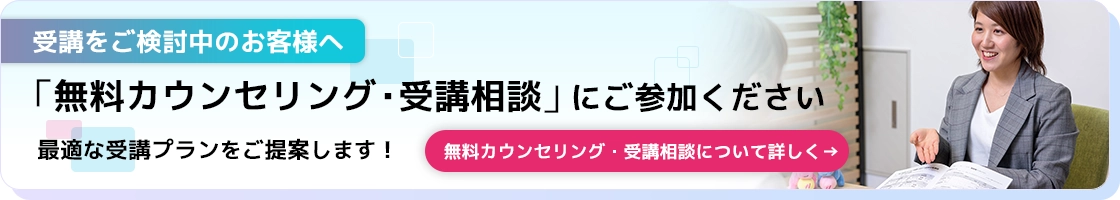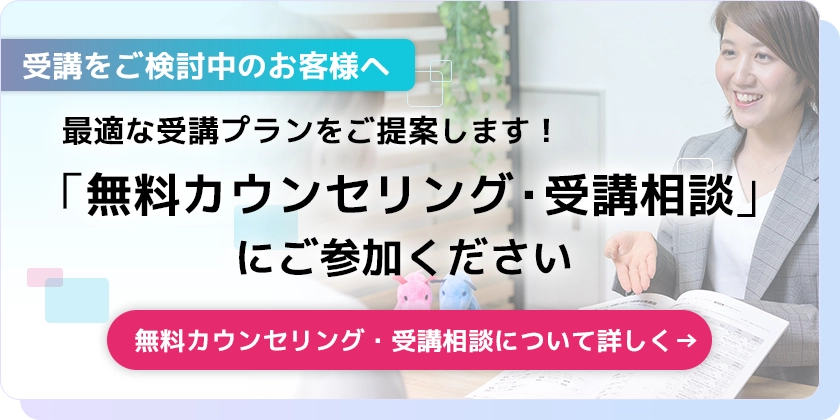ビジネスの現場ではさまざまなシーンで「プレゼンテーション」をおこなう機会があります。「自分はあまり人前で話すのが得意ではないから、プレゼンは苦手・・・」という方も多いのではないでしょうか。もちろん、良いプレゼンをするには「話し方」も重要なキーワードですが、普段の生活でも、耳から入る言葉以上に目で見た情報はとても印象に残ります。今回はそんなビジュアルを意識した「プレゼン資料の作成テクニック」を全3回のシリーズでご紹介します。
文字の「視認性」と「可読性」を意識する

プレゼンをスクリーンで見せる場合、文章ではなく箇条書きで見せることがポイントです。伝えたいことはたくさんあるかもしれませんが、視覚から文字を認識することを考えると、少ない項目で、箇条書きで示す方が効果があります。フォントは、「ゴシック体」がより視認性が高いといわれています。また、行間をしっかりとることも重要です。文字の高さが1としたら、行間を0.7~0.8に設定すると適度な行間となります。
POINT:プレゼンをスクリーンで見せる際に視認性を高めるためには
- 箇条書きで示す
- 項目はなるべく少なくする
- 行間を適切に空ける(引用する)

また、参考文献の引用など、文章(長文)をスライドの中で示さなければならない場合は、「明朝体」の方が読みやすく、可読性が高くなります。ただし、特に必要なければプレゼンのスライド内ではこのような文章は避けた方がよいでしょう。
ジャンプ率を工夫してメッセージを明確化

ジャンプ率を工夫するということは、「伝えたいことをいかに伝えるか」ということです。
ジャンプ率とは、ベースになるものに対して、強調したいものをどの程度強調しているかを表します。
具体例として、文字のサイズにメリハリをつけます。本文の文字サイズに対してタイトルを1.5倍程度、キーメッセージを1.2倍程度に設定します。また、大きさだけではなく色も変化させることで、重要なメッセージを強調することができます。たとえば、本文のテキストを真っ黒ではなくグレーにすることで、サイズだけでなく色のジャンプ率も変化させることができます。
また、要素間の隙間(余白)にもジャンプ率を工夫します。余白をしっかりあけることで、それぞれが別の項目の話であることが明確になります。ただし、同一のユニット構成で、並列したコンテンツ・内容であることを示します。このように、余白にもメリハリが必要となります。